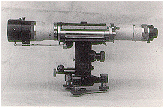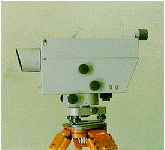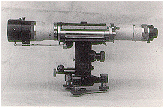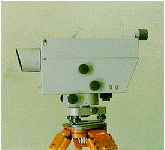高さを求める歴史
|
|
年表 高さを求める歴史
| 西暦 |
和暦 |
記事 |
| 1873年 |
明治 6年 |
東京隅田川河口(霊岸島)において、量水標を設置し潮位観測を開始。 |
| 1876年 |
明治 9年 |
内務省地理局 東京-塩釜(宮城県)の近代的水準測量を実施。 |
| 1883年 |
明治16年 |
参謀本部測量課 東京周辺の精密水準測量を実施。
その後、全国へ水準路線を拡大。 |
| 1891年 |
明治24年 |
東京三宅坂の参謀本部陸地測量部内に水準原点を設置。
陸地測量部が、本格的な潮位観測を開始(油壷、輪島、鮎川、串本、深掘、外浦) |
| 1913年 |
大正 2年 |
全国一等水準網の第1回測量がほぼ完了。 |
| 1923年 |
大正12年 |
関東大震災を契機に第2回測量を開始。
昭和20年までにほぼ改測終了。 |
| 1925年 |
大正14年 |
(このころ)カールツァイスのN3)型精密水準儀及びインバール精密水準標尺の使用がはじまる。 |
| 1928年 |
昭和 3年 |
水準原点の原点数値を改定。(関東大震災による) |
| 1946年 |
昭和21年 |
南海地震を契機に改測を開始。昭和36年までにほぼ改測終了。 |
| 1954年 |
昭和29年 |
(このころ)ウイルドのN3型精密水準儀及びインバール精密水準標尺の使用がはじまる。 |
| 1969年 |
昭和44年 |
「昭和44年度平均成果」を公表。(北海道を除く水準点) |
| 1972年 |
昭和47年 |
「昭和47年度平均成果」を公表。(北海道の水準点) |
| 2002年 |
平成14年 |
「2000年度平均成果」を公表。実測重力値を用いた「正標高補正」を採用 |
| 2011年 |
平成23年 |
水準原点の原点数値を改定。(東北地方太平洋沖地震による)
東日本の水準点測量成果を改定。(東北地方太平洋沖地震による)「測地成果2011」 |
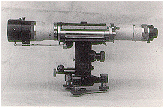 カールツァイス3型精密水準儀
カールツァイス3型精密水準儀
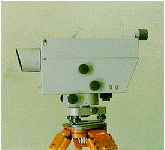 ツァイス社製Ni002型自動水準儀
ツァイス社製Ni002型自動水準儀
|