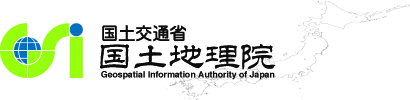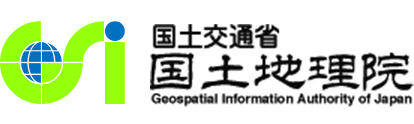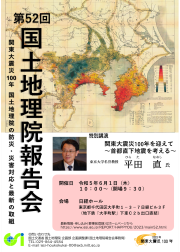OUTLINE開催概要
「第52回国土地理院報告会」は終了いたしました。
令和5年(2023年)6月1日(木)、日経ホール(東京:大手町)において、「第52回国土地理院報告会」を開催しました。また、6月8日(木)から6月30日(金)の期間で、講演をオンデマンド配信いたしました。
「関東大震災100年-国土地理院の防災・災害対応と最新の取組-」をメインテーマに、国土地理院からの取組報告のほか、外部講師による特別講演を行いました。
ご参加いただきましたみなさまに厚く御礼申し上げます。
以下に一般講演の発表資料(PDFファイル)を掲載しております(課題概要下にリンクがございます)。
PROGRAM講演プログラム
特別講演:関東大震災100年を迎えて~首都直下地震を考える~
-
講師:平田 直 氏(東京大学名誉教授)
東京大学名誉教授。
1954年、東京都生まれ。1978年、東京大学理学部地球物理学科卒業。東京大学助手、助教授などを経て、 2009年東京大学地震研究所所長。2011年東京大学地震研究所地震予知研究センター長。2020年退職。 現在、地震調査研究推進本部地震調査委員会委員長。地震防災対策強化地域判定会会長。
主な著書「首都直下地震」(岩波書店)
-

一般講演
-
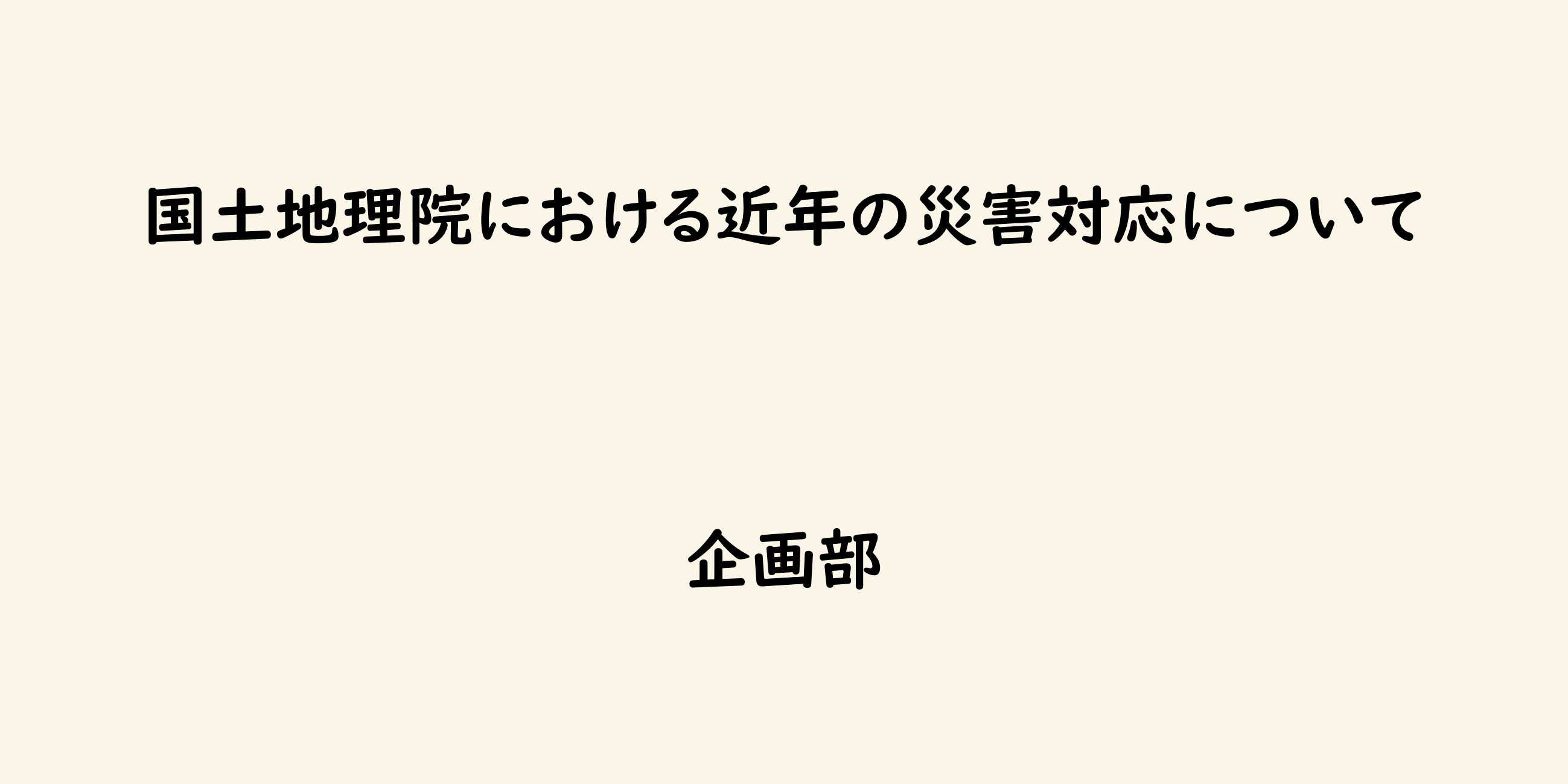 国土地理院は、これまで地震、火山噴火、台風・豪雨等に関する様々な災害対応を行ってきた。近年の災害において国土地理院が作成、提供した情報について概要を報告する。
国土地理院は、これまで地震、火山噴火、台風・豪雨等に関する様々な災害対応を行ってきた。近年の災害において国土地理院が作成、提供した情報について概要を報告する。
-
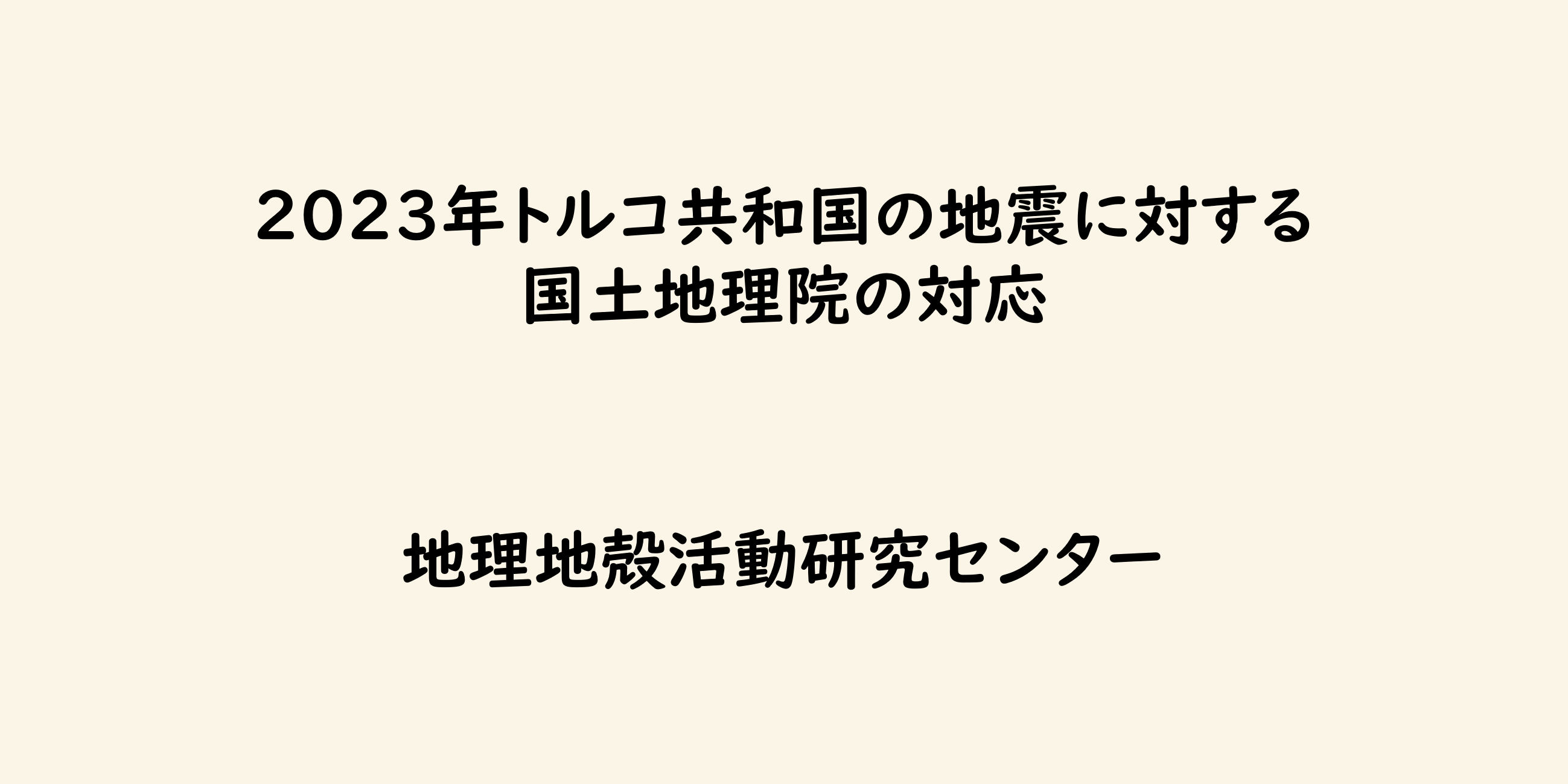 2023年2月6日にトルコ共和国においてM7.7およびM7.6(トルコ防災危機管理庁による)の地震が発生し、大きな被害をもたらした。国土地理院は、地震発生後すぐに、事務局をつとめる地震予知連絡会WGを通じて日本の地球観測衛星「だいち2号」の緊急観測を要請した。また、観測データをいち早く解析し、ホームページ上で公開するとともに、関係機関への周知及びデータ提供を行った。
2023年2月6日にトルコ共和国においてM7.7およびM7.6(トルコ防災危機管理庁による)の地震が発生し、大きな被害をもたらした。国土地理院は、地震発生後すぐに、事務局をつとめる地震予知連絡会WGを通じて日本の地球観測衛星「だいち2号」の緊急観測を要請した。また、観測データをいち早く解析し、ホームページ上で公開するとともに、関係機関への周知及びデータ提供を行った。
本発表では国土地理院の取組を報告するとともに、日本で発生した内陸地震と比較しながら、「だいち2号」で明らかになった地震の概要について報告する。
-
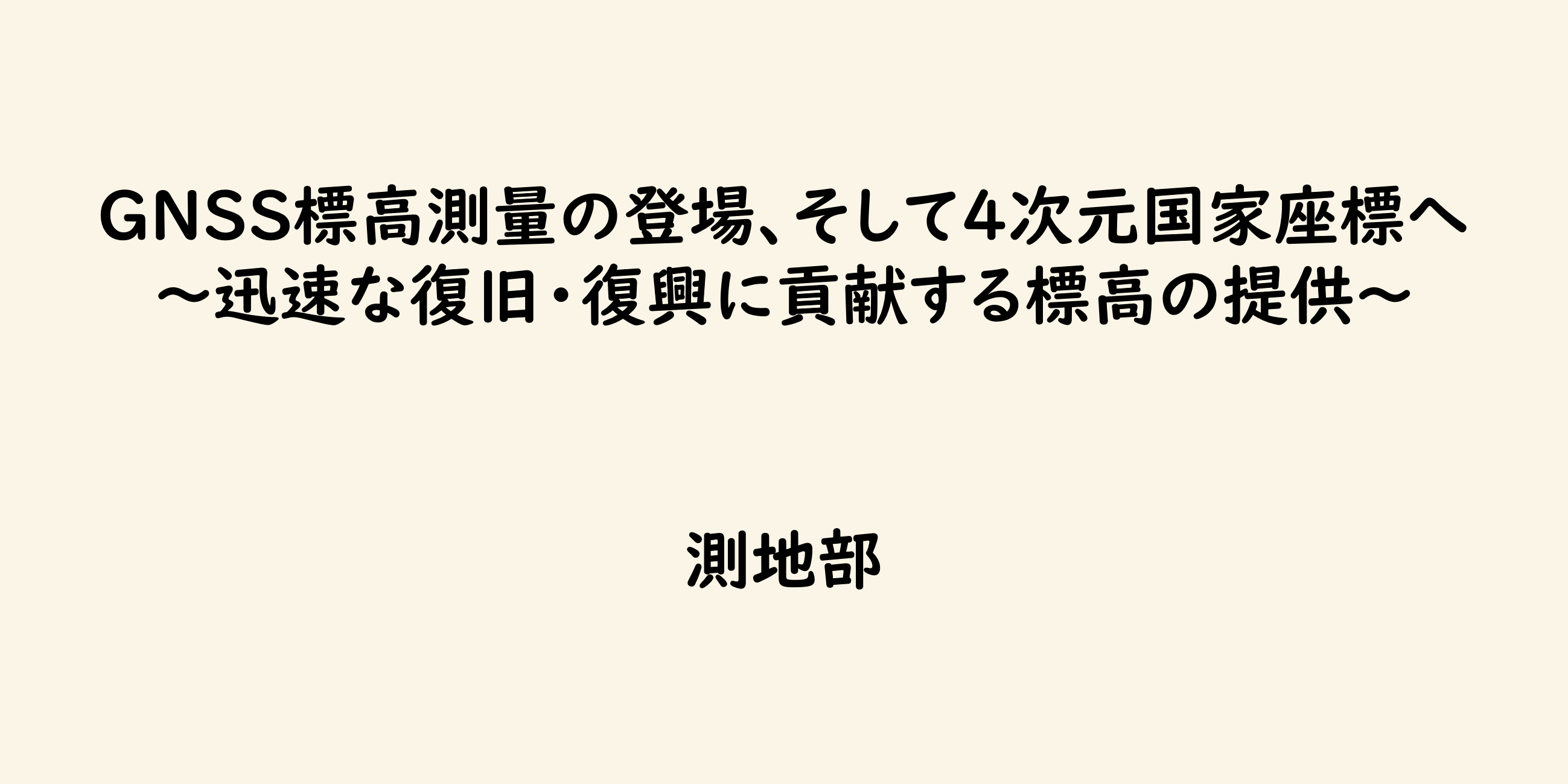 衛星測位で迅速かつ容易な標高決定を実現するため、令和元年度より航空重力測量を開始し、新たな標高の基準となる精密重力ジオイドの整備を進めている。この新たな標高の基準は、デジタル化・リモート化社会推進のための共通基盤であり、公共工事の生産性向上などに寄与することが期待されている。また、災害直後の復旧・復興に必要な標高の提供が可能となる。
衛星測位で迅速かつ容易な標高決定を実現するため、令和元年度より航空重力測量を開始し、新たな標高の基準となる精密重力ジオイドの整備を進めている。この新たな標高の基準は、デジタル化・リモート化社会推進のための共通基盤であり、公共工事の生産性向上などに寄与することが期待されている。また、災害直後の復旧・復興に必要な標高の提供が可能となる。
本報告では、これまでの航空重力測量の取組みや試作した精密重力ジオイドの精度評価などについて紹介する。さらに、精密重力ジオイドを利用する新しい標高の測量手法に関する検討状況や、その実現により国土の任意の場所、任意の時刻で高精度な位置情報を利用できる4次元国家座標の展望についても報告する。
-
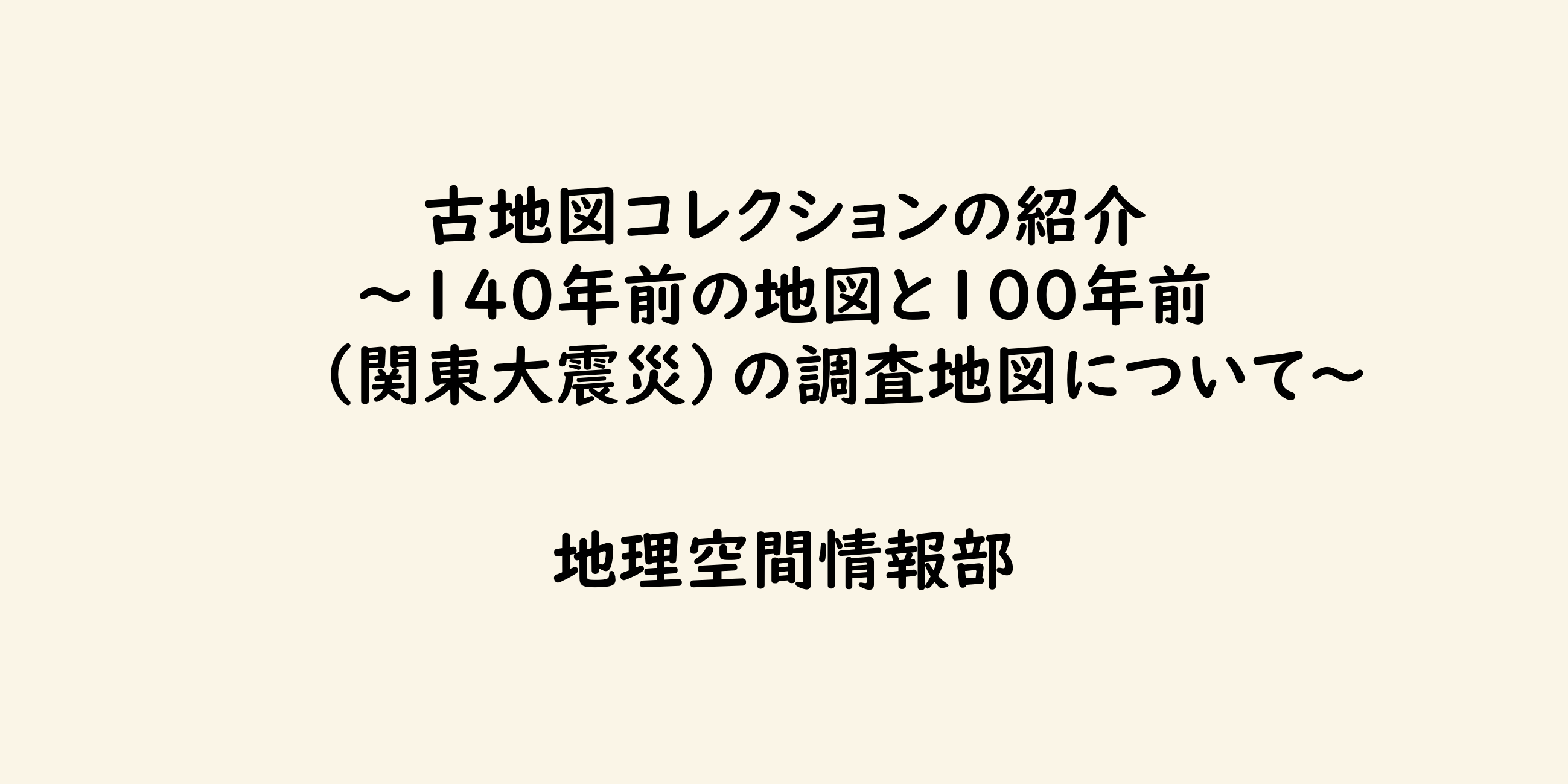 明治13年(1880年)から明治19年(1886年)に作成され、現在も国土地理院でその全ての原版が保存されている迅速測図原図について紹介する。併せて、100年前に発災した関東大震災の被害状況について、国土地理院の前身である陸地測量部が実施した聞き取り調査や現地調査の結果を記載した「震災地応急測図原図」について紹介する。
明治13年(1880年)から明治19年(1886年)に作成され、現在も国土地理院でその全ての原版が保存されている迅速測図原図について紹介する。併せて、100年前に発災した関東大震災の被害状況について、国土地理院の前身である陸地測量部が実施した聞き取り調査や現地調査の結果を記載した「震災地応急測図原図」について紹介する。
-
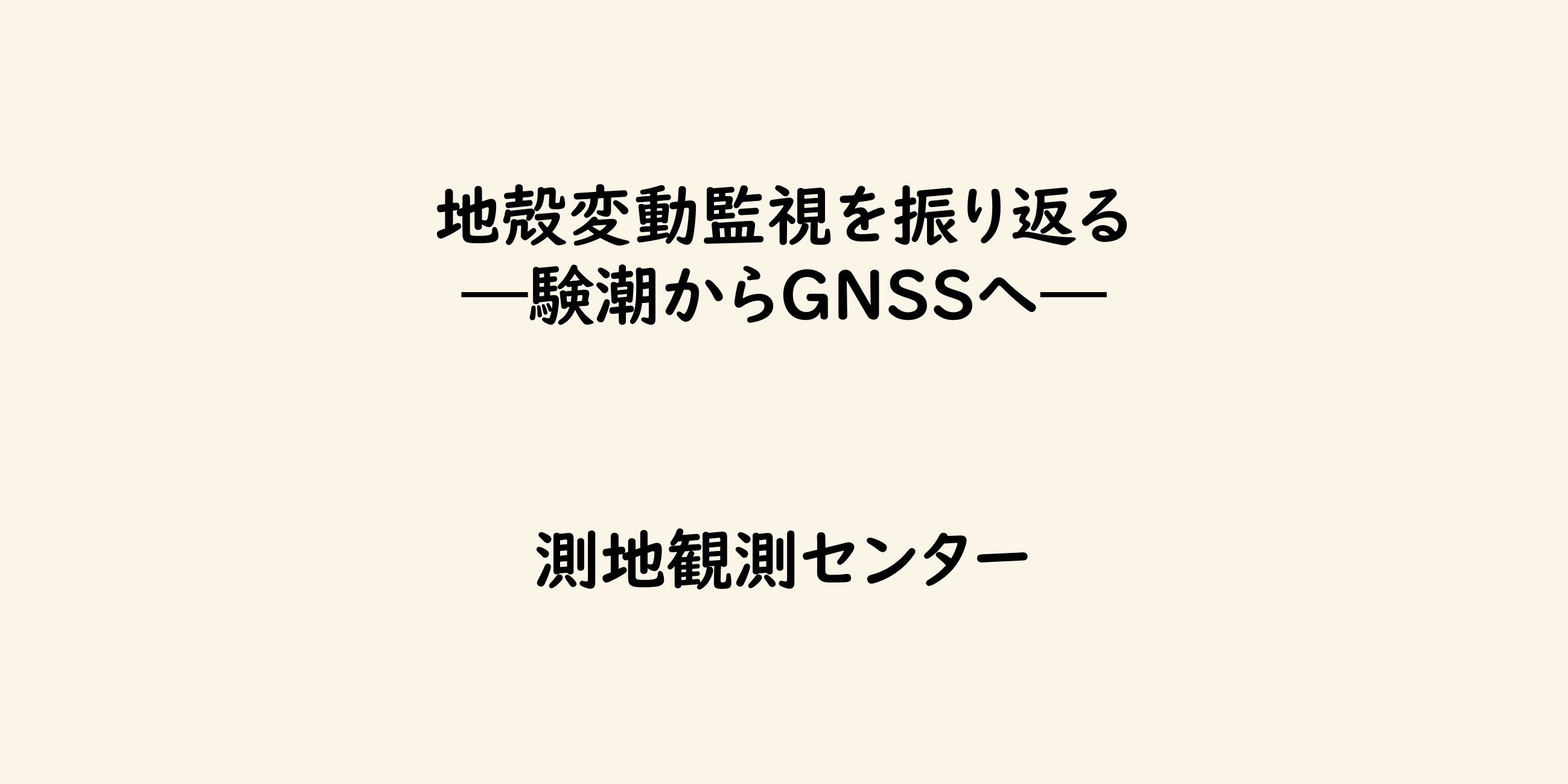 今年、震災から100年目の節目を迎える1923年の関東大震災では広域で地殻変動が確認されていて、神奈川県の油壺験潮場でも約140cmにも及ぶ土地の隆起を捉えていた。
今年、震災から100年目の節目を迎える1923年の関東大震災では広域で地殻変動が確認されていて、神奈川県の油壺験潮場でも約140cmにも及ぶ土地の隆起を捉えていた。
このように験潮場は、水準測量や三角測量とともに地殻変動も捉えるツールとしての役割を長年にわたって果たしてきたが、現在では、1993年から運用が始まった電子基準点(GEONET)が地殻変動監視の中心的な役割を担っている。
本講演では、測地観測センターで所掌する験潮からGEONETへと120年にわたって続く地殻変動監視の歴史について報告する。
-
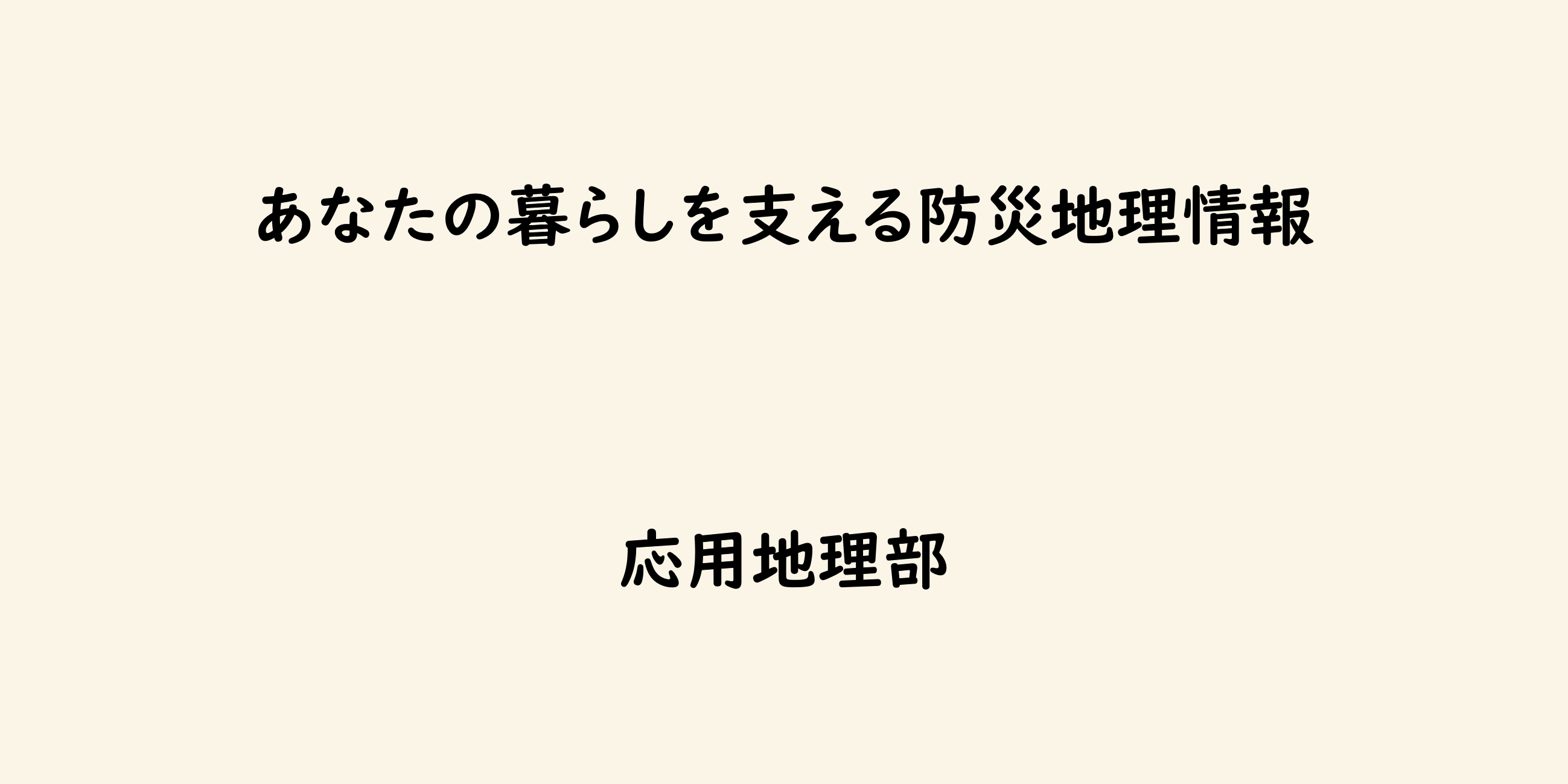 日本は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、昔から数多くの自然災害に見舞われてきた。そして、2023年は関東大震災発生から100 年の節目の年である。
日本は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、昔から数多くの自然災害に見舞われてきた。そして、2023年は関東大震災発生から100 年の節目の年である。
国土地理院では、防災・減災のための「防災地理情報」の整備・充実を図っている。身の回りの土地の成り立ちとその土地が本来持っている自然災害リスクを確認できる「地形分類」や過去に起きた津波や洪水などの自然災害の教訓を伝える「自然災害伝承碑」の整備、教育関係者との連携・教育コンテンツの拡充を図る「防災・地理教育支援」等の取組について紹介する。
-
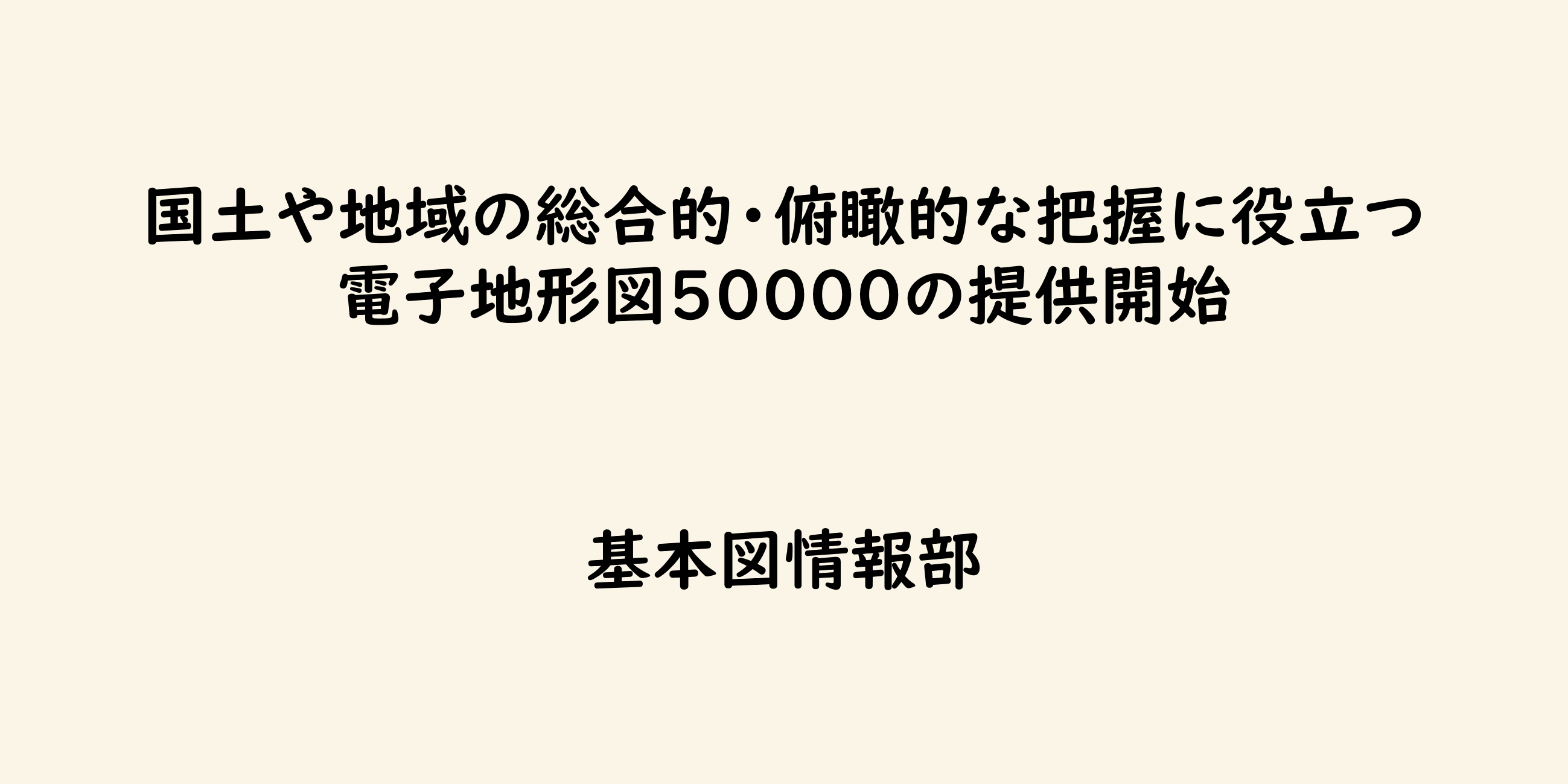 我が国の国土や地域を総合的・俯瞰的に捉える観点で、その現況を適切な縮尺の一図葉で表せることは重要である。「電子国土基本図のあり方検討会」でも、電子国土基本図からの自動処理を基本とした縮尺50000分の1の電子地形図の提供について提言があり、技術的検討を進めてきたところ、この度、「電子地形図50000」の提供を開始した。その意義や経緯、作成手順や表現の仕様、今後の整備計画等について報告する。
我が国の国土や地域を総合的・俯瞰的に捉える観点で、その現況を適切な縮尺の一図葉で表せることは重要である。「電子国土基本図のあり方検討会」でも、電子国土基本図からの自動処理を基本とした縮尺50000分の1の電子地形図の提供について提言があり、技術的検討を進めてきたところ、この度、「電子地形図50000」の提供を開始した。その意義や経緯、作成手順や表現の仕様、今後の整備計画等について報告する。
CONTACTお問い合わせ先
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番国土交通省 国土地理院 企画部 企画調整課
(国土地理院報告会事務局)
E-Mail gsi-houkokukai-00=gxb.mlit.go.jp
(=を@に変更してください)