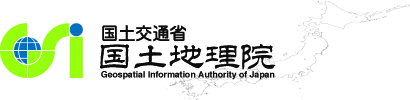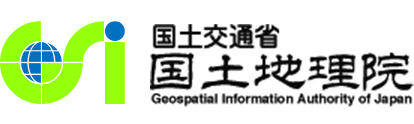令和5年度第15回北海道地区産学官懇談会
道内における地理空間情報の活用推進を目的とした産学官の関係者による懇談会を開催しました
開催報告
北海道地方測量部は、令和5年12月5日(火)に「第15回地理空間情報に関する北海道地区産学官懇談会」(座長:橋本雄一 北海道大学大学院文学研究院教授)をオンライン開催しました。
今後も本懇談会等を通じて産学官関係者の連携を深化させ、道内における地理空間情報の利活用を加速します。
今後も本懇談会等を通じて産学官関係者の連携を深化させ、道内における地理空間情報の利活用を加速します。
日時
令和 5 年 12 月 5 日(火)9:30~11:30
会議形式
オンライン開催(Microsoft Teams)
出席者(敬称略)
【産業界】
磯田 忠雄 北海道 G 空間情報技術研究会会長
木村 直樹 (一社)日本写真測量学会北海道支部役員
小枝 登 (公社)日本測量協会北海道支部技術センター長
((公社)日本測量協会北海道支部長 倉内 公嘉 委員代理)
雫石 和利 (一社)建設コンサルタンツ協会北海道支部情報委員会委員長
藤原 達也 (一社)北海道産学官研究フォーラム副理事長
三好 達也 特定非営利活動法人 Digital 北海道研究会事務局次長
渡辺 亮 (一社)北海道測量設計業協会会長
【学界】
笠井 美青 北海道大学大学院農学研究院准教授
萩原 亨 北海道大学大学院工学研究院教授
橋本 雄一(座長) 北海道大学大学院文学研究院教授
吉村 暢彦 酪農学園大学農食環境学群講師
【官(公的機関)】
林 憲裕 北海道開発局事業振興部調整官
(北海道開発局事業振興部長 井上 勝伸 委員代理)
和田 栄二 北海道建設部建設政策課政策調整担当課長
(北海道建設部建設政策局長 平山 大輔 委員代理)
竹本 新一 札幌市建設局土木部維持担当部長
仲井 博之 国土地理院北海道地方測量部長
【事務局】
国土地理院北海道地方測量部
磯田 忠雄 北海道 G 空間情報技術研究会会長
木村 直樹 (一社)日本写真測量学会北海道支部役員
小枝 登 (公社)日本測量協会北海道支部技術センター長
((公社)日本測量協会北海道支部長 倉内 公嘉 委員代理)
雫石 和利 (一社)建設コンサルタンツ協会北海道支部情報委員会委員長
藤原 達也 (一社)北海道産学官研究フォーラム副理事長
三好 達也 特定非営利活動法人 Digital 北海道研究会事務局次長
渡辺 亮 (一社)北海道測量設計業協会会長
【学界】
笠井 美青 北海道大学大学院農学研究院准教授
萩原 亨 北海道大学大学院工学研究院教授
橋本 雄一(座長) 北海道大学大学院文学研究院教授
吉村 暢彦 酪農学園大学農食環境学群講師
【官(公的機関)】
林 憲裕 北海道開発局事業振興部調整官
(北海道開発局事業振興部長 井上 勝伸 委員代理)
和田 栄二 北海道建設部建設政策課政策調整担当課長
(北海道建設部建設政策局長 平山 大輔 委員代理)
竹本 新一 札幌市建設局土木部維持担当部長
仲井 博之 国土地理院北海道地方測量部長
【事務局】
国土地理院北海道地方測量部
議事
- 開会
- (1)事務局からの報告
・情報共有会合の開催状況報告(資料2)(PDF256KB)
(2)話題提供1
「地理空間情報を活用した研究の紹介」(資料3)(PDF3MB)
(北海道大学大学院農学研究院准教授 笠井 美青)
(3)話題提供2
「私のこれまでの取り組み」(資料4)(PDF3MB)
(酪農学園大学農食環境学群講師 吉村 暢彦)
- 意見交換
- 閉会
(1) 事務局からの報告
・懇談会設置要綱の改正案について(資料1)
本年度の懇談会の開催準備の中で構成員の任期の記載について意見を頂いたことから、設置要綱の改正案を提示したい。「構成員の任期は1年を超えない期間とする。ただし、再任は妨げないこととする。」ということで追記の案の作成を行った。→異議無く満場一致で可決決定された。
・情報共有会合の開催状況報告(資料2)
今年度は2回実施済み。今後も地理空間情報の利用が進むことが考えられるため、国土地理院としても皆様の業務等の一助になるよう、引き続き意見交換や話題提供の場として情報共有会合を開催したいと考えている。
(2) 話題提供1「地理空間情報を活用した研究の紹介」北海道大学大学院農学研究院准教授 笠井 美青
資料3に沿って話題提供が行われた。
(3) 話題提供2「私のこれまでの取り組み」酪農学園大学農食環境学群講師 吉村 暢彦
資料4に沿って話題提供が行われた。
質疑応答
資料3、資料4の話題提供後に行われた質疑応答及び意見交換は以下のとおり。
【質問】
航空レーザーのデータのエラーは具体的にどのようなエラーが発生するのか。
【回答】
レーザー光が地表まで到達していない事があり、木の下の地表がどのぐらい荒れているのか把握できない(エラーが発生する)ことがある。
【質問】
(前述の質問に対して)逆に木があっても地表を測定できることに驚いたが、近年では精度的に向上しているのか。
【回答】
精度は向上している。特にUAVを用いると地上から至近距離でレーザー光を落とすことができるため、かなりいいデータを取得できるようになった。
【質問】
技術が高度化しているなかで、学生に技術を伝える難しさを感じるが、その点で両先生にコメントをお願いしたい。
【回答1】
解析データで考えている間に現実とかけ離れてしまうことがある。そのため、現場に行って考えさせるよう努力している。
【回答2】
技術だけを教えても応用が難しいため、社会の現象の捉え方、見るスキルを育みながらGIS的な考え方を伝えるというところに自分としては注目している。
意見交換
各委員へGISや地理空間情報の活用に関係する意見や組織における取組状況などの報告を行った。発言内容、及び質疑応答は以下のとおり。
◯委員
感想という形で話をさせていただきたい。笠井先生のご発表の件からは、私どもは防災事業を所掌していることから非常に興味の深いところであった。土塊の動きや土砂の動きが事前にわかるようであれば、とても助かると感じた。吉村先生からの発表からはGISに絡むいろいろな話題をしていただき、特に小樽の観光の件は興味深く感じた。
◯委員
主に防災事業の視点のところで津波浸水想定、土砂災害警戒区域の指定する際の基図として地理空間情報を利用している。また、土砂災害、土砂洪水範囲の災害リスクの高まりに対しての発生確率の高い地域を抽出するために航空レーザー測量をして効果的な砂防施設の整備を進めている。さらにダムの貯水池の周辺の地すべり調査でGISを用いて傾斜量解析、地形の曲率解析を行い、微地形表現図を作成している。
高校の地理総合が必須になったということだが、平成30年から毎年、主に担い手確保という視点から、高校生を対象としたICTの体験講習会などを実施。今年については苫小牧工業高校のほか、5校で開催する予定である。
◯委員
道路の維持管理にGISを活用した総合道路管理システムを運用している。システムは道路行政に関わる職員が利用可能、道路整備計画の策定や道路維持管理業務などのさまざまな用途に利用され、職員の業務効率化にも寄与している。今後、この懇談会を通じて情報の効果的な活用を進めて参りたいと考えている。
◯委員
測量設計関係で注目されている3次元GIS、3次元に関わる測量技術、Icon、BIM/CIMによる3次元測量、3次元設計、Web GISの最新情報などを、この10月に全国大会において参加するなど、先行して我々の団体がGISに関わり、全国で活動している。
10月の作業規程の改定があり、ドローンレーザー、地上レーザーという3次元の点群測量が入ってきたということで、多くの測量技術者が今注目されており、測量設計はこれから大きく変わっていくということを申し添えたい。
◯委員
測量業者の現場で取得するさまざまな測量データ、特に今、UAV、レーザースキャナーを使ったビッグデータが使えるようになってきたため、測量計画機関が求める品質や精度確認と、2次利用者が利用に困らないような、基準に適合した測量成果となるべく、測量計画機関の職員及び測量作業機関の技術者を対象として、データの取得方法や処理方法に関する基礎的な技術に関する基礎講座の講習会を年間に25本程度行っている。
今後、地理空間情報の2次利用を通じて測量や地図の魅力に興味を持っていただいて、業界の人材確保につながることを期待したい。
◯委員
担い手確保に向けた業界PR活動として、学校訪問による測量の出前授業を継続している。来年の「建設産業ふれあい展」では、スマホのLiDAR技術による3D測量体験を実施。3D測量のスタンダード化が進む中、精度管理の問題などから、理想的なデータ共有には至っていない。国土地理院からi-Construction推進のための3次元数値地形データ作成マニュアルが発行され、測量業界としては3Dに向かっているが、精度管理の問題は依然として課題。目的に応じたデータの取得と活用が重要と考えている。
◯委員
年間3回の講演会と不定期の現地見学会を開催し、写真測量、リモートセンシング、GIS、マシンビジョンなどの技術や知識を広めている。今年度は、写真測量を含む測量に関する講演会や、3次元機械学習に関する講演会を開催した。3月ごろには学術講演会を開催する予定である。今後も、北海道の測量業をはじめ地理空間情報に関連する分野の発展や地理教育を含む人材育成に貢献していきたいと考えている。
◯委員
GIS講習会を継続実施している。GISなどの技術は、誰でも簡単に使えるようになってきた。今後は、発想力や応用力を身に付けることが課題である。
◯委員
「GIS Day in オホーツク2023」が2023年12月8日に開催される。基調講演は、北海道大学の橋本教授が担当する。ハンズオン講習会も開催される。すでに300名以上が申し込んでおり、現地参加者も40名ほど見込まれている。「GIS Day」は、北海道で年に3回開催されており、来年も函館で開催される予定。GISの普及活動を積極的に推進しており、ハンズオン講習会も含めて、定期的に全道で展開していく方針。
◯委員
リモートセンシングとGISの普及活動を行っており、今年、来年度以降も定期的にGISハンズオン講習会を開催していく。高校生の地理科目必履修化をチャンスと捉え、活動を通じて学生への地理空間情報の普及活動を推進し、測量業界への人材確保につなげてゆきたい。
◯委員
GISを使って長らく地形解析をしてきたが、GIS学会には入っておらず、情報収集が限られていた。今回の懇談会に参加したことで、さまざまな関連者から話を聞いて、自分の研究の方向性や需要について考えるきっかけになった。GISの世界は広くて深いので、今後もさまざまな人と情報共有していきたい。
◯委員
GISは以前発表させていただいたが、デジタルツインで冬の道路管理ということで、いろいろな気象情報、視界情報、道路情報をセンシングし、アップロードし、データ処理し、関係者の方に配布し、道路管理に貢献していくということ行わせていただいている。そのうち、また進捗を報告したい。
◯委員
データの入手コストが高騰している。データの共有を進めることで、コスト削減や利活用の促進につなげたい。また、さまざまなネットワークを構築することで、データの収集や活用の効率化を図りたい。
◯委員
今、地理空間情報の高度活用社会を目指す段階にあり、いろいろな技術やデータの社会実装が進められつつある。その中で心配なのが、使う者のリテラシーを上げなくてはいけないということ。地図教育、地図データリテラシーを上げるための教育の必要があると感じた。
地図を供給する側は、使い易いばかりではなくて、精度が正しく示され、精度的に用途が示されているもの、精度的に保証されたものが出回っていくというのが良いのではないか。そういう体制づくりもまた重要である。
本懇談会の機会を利用して今後も地理空間情報の高度活用社会に向けた議論を進めていきたい。
◯委員
笠井先生の発表では、測量技術や地理空間情報が防災分野にも貢献できるのではないかと今後の進展に期待したいと感じた。
吉村先生には、GISを用いて可視化することによっていろいろな面で有効性を示していただき、大変勉強になった。
本懇談会は北海道管内の国、地方公共団体、測量や地理空間情報関係の業界団体、研究者など組織と関係を構築するためのコミュニケーションの場である。これからも情報共有を図りつつ意見交換することで、北海道内においてGISや地理空間情報の活用が一層進むことを願う。
各委員から国土地理院への本懇談会関連の質問及び要望の発言は以下のとおり。
【質問】
つい最近、1メートルのDEMデータ公開がされたが、今後の展開、どのぐらいのスピード感で拡大していくか。
【回答】
国土地理院は、3次元地図化やデータの共有を進めていく計画である。航空レーザー測量や、他の機関や都道府県が保有するデータの活用を検討。具体的な実施方法は、まだ検討中である。
【要望】
国土地理院の地図は、データの正確性や信頼性が高いが、外見があまりよくないと指摘されている。Google マップのように意匠、デザイン、外見改善をお願いしたい。
【回答】
ご意見を承る。
【要望】
高校の先生から、地理院地図のプリント機能に関する要望が出ている。具体的には、以下の点が要望されている。「任意の範囲と縮尺でプリントできるようにする」、「プリントする際に、UTM座標系に変換できるようにする」。これらの要望が実現されれば、地理院地図を教育現場でより活用しやすくなることが期待される。
【回答】
ご意見をもとに、つくばのほうに相談する。
【意見】
(前述の橋本座長の話に続いて)デジタル地図を印刷する際に、縮尺を合わせるのは難しいため、UTMグリッドの使い方を広く周知することが良い。
・懇談会設置要綱の改正案について(資料1)
本年度の懇談会の開催準備の中で構成員の任期の記載について意見を頂いたことから、設置要綱の改正案を提示したい。「構成員の任期は1年を超えない期間とする。ただし、再任は妨げないこととする。」ということで追記の案の作成を行った。→異議無く満場一致で可決決定された。
・情報共有会合の開催状況報告(資料2)
今年度は2回実施済み。今後も地理空間情報の利用が進むことが考えられるため、国土地理院としても皆様の業務等の一助になるよう、引き続き意見交換や話題提供の場として情報共有会合を開催したいと考えている。
(2) 話題提供1「地理空間情報を活用した研究の紹介」北海道大学大学院農学研究院准教授 笠井 美青
資料3に沿って話題提供が行われた。
(3) 話題提供2「私のこれまでの取り組み」酪農学園大学農食環境学群講師 吉村 暢彦
資料4に沿って話題提供が行われた。
質疑応答
資料3、資料4の話題提供後に行われた質疑応答及び意見交換は以下のとおり。
【質問】
航空レーザーのデータのエラーは具体的にどのようなエラーが発生するのか。
【回答】
レーザー光が地表まで到達していない事があり、木の下の地表がどのぐらい荒れているのか把握できない(エラーが発生する)ことがある。
【質問】
(前述の質問に対して)逆に木があっても地表を測定できることに驚いたが、近年では精度的に向上しているのか。
【回答】
精度は向上している。特にUAVを用いると地上から至近距離でレーザー光を落とすことができるため、かなりいいデータを取得できるようになった。
【質問】
技術が高度化しているなかで、学生に技術を伝える難しさを感じるが、その点で両先生にコメントをお願いしたい。
【回答1】
解析データで考えている間に現実とかけ離れてしまうことがある。そのため、現場に行って考えさせるよう努力している。
【回答2】
技術だけを教えても応用が難しいため、社会の現象の捉え方、見るスキルを育みながらGIS的な考え方を伝えるというところに自分としては注目している。
意見交換
各委員へGISや地理空間情報の活用に関係する意見や組織における取組状況などの報告を行った。発言内容、及び質疑応答は以下のとおり。
◯委員
感想という形で話をさせていただきたい。笠井先生のご発表の件からは、私どもは防災事業を所掌していることから非常に興味の深いところであった。土塊の動きや土砂の動きが事前にわかるようであれば、とても助かると感じた。吉村先生からの発表からはGISに絡むいろいろな話題をしていただき、特に小樽の観光の件は興味深く感じた。
◯委員
主に防災事業の視点のところで津波浸水想定、土砂災害警戒区域の指定する際の基図として地理空間情報を利用している。また、土砂災害、土砂洪水範囲の災害リスクの高まりに対しての発生確率の高い地域を抽出するために航空レーザー測量をして効果的な砂防施設の整備を進めている。さらにダムの貯水池の周辺の地すべり調査でGISを用いて傾斜量解析、地形の曲率解析を行い、微地形表現図を作成している。
高校の地理総合が必須になったということだが、平成30年から毎年、主に担い手確保という視点から、高校生を対象としたICTの体験講習会などを実施。今年については苫小牧工業高校のほか、5校で開催する予定である。
◯委員
道路の維持管理にGISを活用した総合道路管理システムを運用している。システムは道路行政に関わる職員が利用可能、道路整備計画の策定や道路維持管理業務などのさまざまな用途に利用され、職員の業務効率化にも寄与している。今後、この懇談会を通じて情報の効果的な活用を進めて参りたいと考えている。
◯委員
測量設計関係で注目されている3次元GIS、3次元に関わる測量技術、Icon、BIM/CIMによる3次元測量、3次元設計、Web GISの最新情報などを、この10月に全国大会において参加するなど、先行して我々の団体がGISに関わり、全国で活動している。
10月の作業規程の改定があり、ドローンレーザー、地上レーザーという3次元の点群測量が入ってきたということで、多くの測量技術者が今注目されており、測量設計はこれから大きく変わっていくということを申し添えたい。
◯委員
測量業者の現場で取得するさまざまな測量データ、特に今、UAV、レーザースキャナーを使ったビッグデータが使えるようになってきたため、測量計画機関が求める品質や精度確認と、2次利用者が利用に困らないような、基準に適合した測量成果となるべく、測量計画機関の職員及び測量作業機関の技術者を対象として、データの取得方法や処理方法に関する基礎的な技術に関する基礎講座の講習会を年間に25本程度行っている。
今後、地理空間情報の2次利用を通じて測量や地図の魅力に興味を持っていただいて、業界の人材確保につながることを期待したい。
◯委員
担い手確保に向けた業界PR活動として、学校訪問による測量の出前授業を継続している。来年の「建設産業ふれあい展」では、スマホのLiDAR技術による3D測量体験を実施。3D測量のスタンダード化が進む中、精度管理の問題などから、理想的なデータ共有には至っていない。国土地理院からi-Construction推進のための3次元数値地形データ作成マニュアルが発行され、測量業界としては3Dに向かっているが、精度管理の問題は依然として課題。目的に応じたデータの取得と活用が重要と考えている。
◯委員
年間3回の講演会と不定期の現地見学会を開催し、写真測量、リモートセンシング、GIS、マシンビジョンなどの技術や知識を広めている。今年度は、写真測量を含む測量に関する講演会や、3次元機械学習に関する講演会を開催した。3月ごろには学術講演会を開催する予定である。今後も、北海道の測量業をはじめ地理空間情報に関連する分野の発展や地理教育を含む人材育成に貢献していきたいと考えている。
◯委員
GIS講習会を継続実施している。GISなどの技術は、誰でも簡単に使えるようになってきた。今後は、発想力や応用力を身に付けることが課題である。
◯委員
「GIS Day in オホーツク2023」が2023年12月8日に開催される。基調講演は、北海道大学の橋本教授が担当する。ハンズオン講習会も開催される。すでに300名以上が申し込んでおり、現地参加者も40名ほど見込まれている。「GIS Day」は、北海道で年に3回開催されており、来年も函館で開催される予定。GISの普及活動を積極的に推進しており、ハンズオン講習会も含めて、定期的に全道で展開していく方針。
◯委員
リモートセンシングとGISの普及活動を行っており、今年、来年度以降も定期的にGISハンズオン講習会を開催していく。高校生の地理科目必履修化をチャンスと捉え、活動を通じて学生への地理空間情報の普及活動を推進し、測量業界への人材確保につなげてゆきたい。
◯委員
GISを使って長らく地形解析をしてきたが、GIS学会には入っておらず、情報収集が限られていた。今回の懇談会に参加したことで、さまざまな関連者から話を聞いて、自分の研究の方向性や需要について考えるきっかけになった。GISの世界は広くて深いので、今後もさまざまな人と情報共有していきたい。
◯委員
GISは以前発表させていただいたが、デジタルツインで冬の道路管理ということで、いろいろな気象情報、視界情報、道路情報をセンシングし、アップロードし、データ処理し、関係者の方に配布し、道路管理に貢献していくということ行わせていただいている。そのうち、また進捗を報告したい。
◯委員
データの入手コストが高騰している。データの共有を進めることで、コスト削減や利活用の促進につなげたい。また、さまざまなネットワークを構築することで、データの収集や活用の効率化を図りたい。
◯委員
今、地理空間情報の高度活用社会を目指す段階にあり、いろいろな技術やデータの社会実装が進められつつある。その中で心配なのが、使う者のリテラシーを上げなくてはいけないということ。地図教育、地図データリテラシーを上げるための教育の必要があると感じた。
地図を供給する側は、使い易いばかりではなくて、精度が正しく示され、精度的に用途が示されているもの、精度的に保証されたものが出回っていくというのが良いのではないか。そういう体制づくりもまた重要である。
本懇談会の機会を利用して今後も地理空間情報の高度活用社会に向けた議論を進めていきたい。
◯委員
笠井先生の発表では、測量技術や地理空間情報が防災分野にも貢献できるのではないかと今後の進展に期待したいと感じた。
吉村先生には、GISを用いて可視化することによっていろいろな面で有効性を示していただき、大変勉強になった。
本懇談会は北海道管内の国、地方公共団体、測量や地理空間情報関係の業界団体、研究者など組織と関係を構築するためのコミュニケーションの場である。これからも情報共有を図りつつ意見交換することで、北海道内においてGISや地理空間情報の活用が一層進むことを願う。
各委員から国土地理院への本懇談会関連の質問及び要望の発言は以下のとおり。
【質問】
つい最近、1メートルのDEMデータ公開がされたが、今後の展開、どのぐらいのスピード感で拡大していくか。
【回答】
国土地理院は、3次元地図化やデータの共有を進めていく計画である。航空レーザー測量や、他の機関や都道府県が保有するデータの活用を検討。具体的な実施方法は、まだ検討中である。
【要望】
国土地理院の地図は、データの正確性や信頼性が高いが、外見があまりよくないと指摘されている。Google マップのように意匠、デザイン、外見改善をお願いしたい。
【回答】
ご意見を承る。
【要望】
高校の先生から、地理院地図のプリント機能に関する要望が出ている。具体的には、以下の点が要望されている。「任意の範囲と縮尺でプリントできるようにする」、「プリントする際に、UTM座標系に変換できるようにする」。これらの要望が実現されれば、地理院地図を教育現場でより活用しやすくなることが期待される。
【回答】
ご意見をもとに、つくばのほうに相談する。
【意見】
(前述の橋本座長の話に続いて)デジタル地図を印刷する際に、縮尺を合わせるのは難しいため、UTMグリッドの使い方を広く周知することが良い。